
「不偏不易」
流祖は、利休時代より始まる「茶禅一味」に代表される精神修養的な茶道感では無く、一服の茶から生まれた人と人の礼法を説きました。
礼とは何か?原点となった茶の礼法とは?
お茶の稽古では、必ず作法を行います。
稽古で必ず行うからこそ、その必要性を追求すべきと。
その原点に立ち返り、偏る以前の茶の作法を追い求めました。
それが流祖の言葉の「不偏不易」に表れています。
詩に、
※「茶の湯には、何伝ふ言の葉も、為さざるにこそ道はありけれ。茶の湯には、何象らん武蔵野の、隈なき月に心成らずや。」
茶の湯とは伝わる言葉だけに偏らず、その場の調和にこそ道であり、そして求めるものは武蔵野のような広々とした大地に、隈なく輝やく光のような心でありたいなと。
流祖は、
師から伝わる茶法がこれ以上偏りができないよう、また茶法の形骸化が進まないように熟考し、何にも偏らず変わらない心で一服の茶の式礼を追い求めたのです。
唐物、和物茶入を帛でふく理とは?
これが茶の礼法が生まれた原点。
形を無くす事は簡単ですが、
一番心の重要なところです。
必ず稽古で、心得ていきたい根幹の部分だと思います。




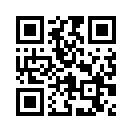
この記事へのコメント
茶禅一味では無く、人と人との礼を
重んじるというのが興味深く感じました。
当方、岩手県に住む者で、三千家の
1つの流派を習っておりますが、
速水流の公家文化を取り入れた雅な茶の湯にも関心があります。
しかし、最も近い教室が東京という
ことで、残念に思っております
この記事へコメントする